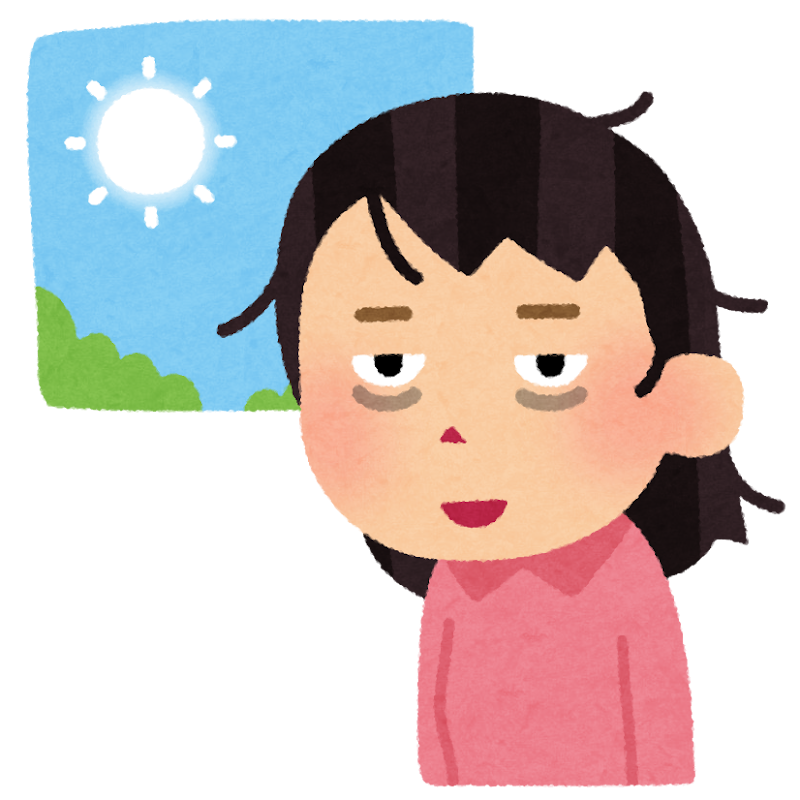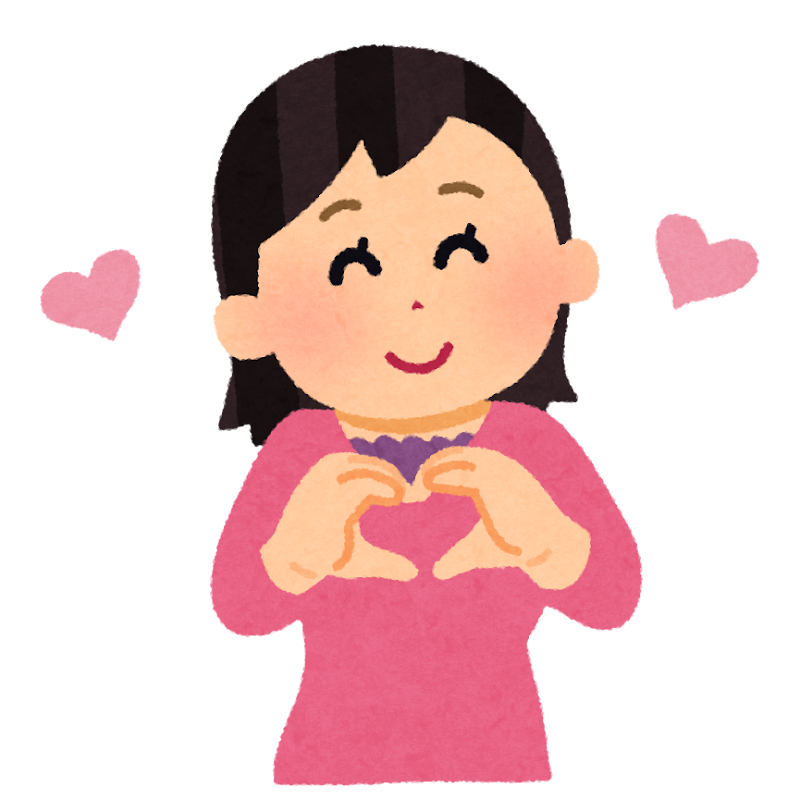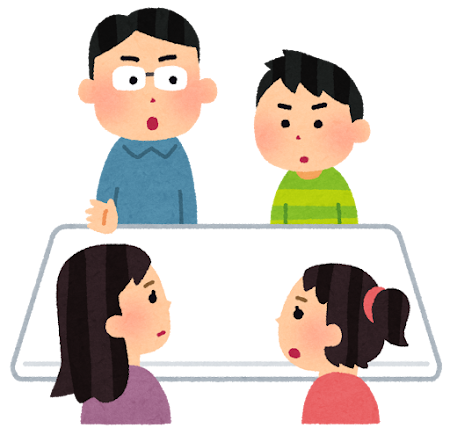ここ数年、私が毎週楽しみにしていたYouTube動画のひとつに、60代の女性が一人暮らしの日常を淡々と記録した「Miko’sライフ」というチャンネルがありました。その動画は、特別な演出や過剰な編集があるわけでもなく、丁寧に暮らす一人の女性の普通の生活を映し出していました。
洗練された生活スタイルや心豊かな趣味に憧れ、毎週その動画を観るたびに、自分の日常を振り返り、もっと丁寧に暮らしたいという気持ちにさせられていました。同じように感じていた視聴者は、きっと私だけではなかったはずです。
ところが、ある日ふと気づくと、その動画が最近アップされていないことに気づきました。それまでは毎週決まった時間に新しい動画が投稿されていたのですが、次第に投稿の間隔が不定期になり、ついには新しい動画が一切投稿されなくなったのです。そして、これまでの動画も探しても見つからなくなりました。削除されてしまったようです。
これにはとても驚きました。あんなに丁寧に視聴者のコメントに対応していたMikoさんが、いきなりチャンネルを閉鎖するような行動を取るとは考えにくかったからです。「何があったのだろう?」と、さまざまな可能性を思い巡らせました。
もしご病気や何か事情があったとしても、これまでの動画を削除する理由は見当たりません。Mikoさんは、主婦としての知恵を活かした「ずぼら味噌汁」や、冷凍保存可能な野菜を使った簡単で工夫に満ちた料理を紹介するなど、多くの人々に役立つ情報を提供していました。登録者数も数万人にのぼっており、動画を残しておけばさらに多くの人が視聴したことでしょう。それにもかかわらず、動画をすべて削除してしまった理由が気になって仕方ありませんでした。
Mikoさんの生活ぶりは、素敵なマンションでの充実した一人暮らしでした。ご主人を数年前に亡くされ、娘さんたちも独立されている中で、ジムや英会話、ドラムの練習、公園でのウォーキングと、多彩な趣味を楽しんでおられました。その様子には多くの視聴者が元気をもらい、共感していたと思います。しかし同時に、彼女の充実した暮らしぶりが、一部の心ない人々の嫉妬や攻撃の的になってしまったのではないかという思いも拭えません。
他の60代女性が日常を記録した動画にたどり着いた際、そこにはひどいコメントに悩まされているという投稿者の言葉がありました。それを見て、「もしかするとMikoさんも、同じように嫌がらせを受けてしまったのでは?」という疑念が確信に変わりました。仮にそのような事情であれば、あれほど丁寧に視聴者と交流し、コメントにも真摯に対応されていたMikoさんが、すべての動画を削除する決断をされた理由も、理解できる気がします。
それでも、突然の閉鎖に対しては、裏切られたような寂しい気持ちが拭えません。Mikoさんに何があったのか、どんなつらい思いをされたのか、何も知ることができないままというのは悲しいことです。しかし同時に、そうした決断に至るまでのMikoさんの苦しみや葛藤を思うと、胸が痛みます。
動画を通して感じられたのは、彼女の生活の丁寧さだけではなく、心の豊かさでした。視聴者との信頼を築きながら、動画を通じて日常の幸せを分けてくださったMikoさんには感謝の気持ちしかありません。もしもまたいつか、Mikoさんの暮らしの一端に触れる機会があれば、こんなにうれしいことはありません。
最後に、Mikoさんがご自身のペースで、心穏やかな毎日を過ごされていることを願っています。